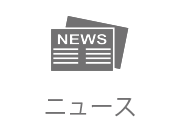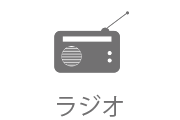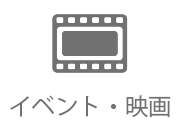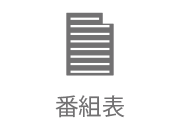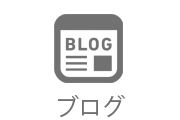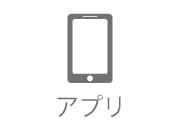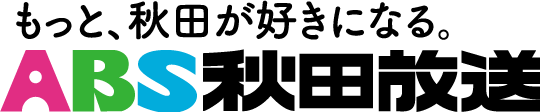知っトク医療のつぼ バックナンバー
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 【12/26放送】やけどや擦り傷を負ったら・・・どうする?
【12/26放送】やけどや擦り傷を負ったら・・・どうする?秋田大学医学部附属病院 中永士師明さん
料理をしていて熱い油がはねたり、はさみで作業をしていたり・・・日常生活のちょっとしたアクシデントで起きてしまう「やけど」や擦り傷・切り傷などの「けが」。救急の対処法を知らずに、適切な処置がとられなければ、感染などにより命に関わってしまうこともあります。番組では、やけどやけがをした時にどのような症状が見られるのか、またその時にどういった手当てをすればよいのか、病院に行く際のポイントなどについて秋田学医学部附属病院・救急科の中永士師明さんに伺いました。
 【12/19放送】もしも窒息したら!正しい知識を身につけよう
【12/19放送】もしも窒息したら!正しい知識を身につけよう秋田大学医学部附属病院 五十嵐季子さん
もしも身近な人が食べ物を詰まらせたら、あなたはどんな対応をとることができますか。日本では、1年間に約4000人が食べ物による窒息で亡くなっているといいます。窒息は特別な食べ物で起こるわけではなく、私たちが普段食べている食事で起こります。しかし、ただちに対処しなければ、呼吸停止から心停止にいたる緊急事態なのです。番組では窒息を起こした時には、どのような症状が見られるのか、またその時どういった手当てをすればよいのかを秋田学医学部附属病院・救急科の五十嵐季子さんに伺いました。
 【12/12放送】チアノーゼ〜この症状を見落とすと危険〜
【12/12放送】チアノーゼ〜この症状を見落とすと危険〜秋田大学医学部附属病院 本川真美加さん
今回は子どもの心臓病・先天性心疾患をテーマにお送りします。先天性心疾患は、生まれつき心臓の形や機能に異常がみられる病気のことをいい、新生児100人に1人が発症します。先天性心疾患のヒントとなるのがチアノーゼという症状です。チアノーゼは、皮ふや粘膜が青紫色になる状態で、血液中の酸素濃度が低下したときに手先や口の周りに症状が現れやすくなるといいます。秋田学医学部附属病院・心臓血管外科の本川真美加さんになぜチアノーゼが起きるのか、また先天性疾患の治療法などについて伺いました。
 【12/5放送】息苦しくなったら要注意・・・心臓弁膜症
【12/5放送】息苦しくなったら要注意・・・心臓弁膜症秋田大学医学部附属病院 山浦玄武さん
今回は心臓弁膜症をテーマにお送りします。心臓弁膜症は、心臓の弁の機能が正常に働かなくなってしまう病気です。心臓の病気のなかでも、心筋こうそくや狭心症と並んで多い病気で、放っておくと心不全を起こしたり、動悸(どうき)や胸痛、突然死を起こす可能性もあるといいます。心臓弁膜症がなぜ起きてしまうのか、診断ではどのような検査が行われるのか、また手術を中心とした治療法について秋田大学医学部附属病院・心臓血管外科の山浦玄武さんに話を伺いました。
 【11/28放送】胸の激しい痛み・・・狭心症
【11/28放送】胸の激しい痛み・・・狭心症秋田大学医学部附属病院 石橋和幸さん
テーマは「狭心症」。安静にしていると数分で改善するものの、「階段を上った時に胸が強く圧迫されるような苦しさがある」というような症状がたびたび見られる人は注意が必要だといいます。心臓は私たちの体のなかで、生命にかかわる重要な臓器です。狭心症は、心臓の周りにある冠動脈と呼ばれる血管が動脈硬化や血栓などで狭くなったりふさがったりしてしまう病気です。この病気の症状や、カテーテルという細い管を通して冠動脈を広げる手術や冠動脈のバイパス手術などの治療法について秋田大学医学部附属病院・心臓血管外科の石橋和幸医師に話を伺いました。
 【11/21放送】病気をうつさない もらわない感染制御(2)
【11/21放送】病気をうつさない もらわない感染制御(2)秋田大学医学部附属病院 加賀谷英彰さん・小林則子さん
2回シリーズの院内感染を防ぐ取り組み「感染制御」の2回目で、「感染を防ぐための薬剤師や検査技師の取り組み」を取り上げます。薬剤師は、感染症を治療中の患者に薬剤を投与する際、治療に合っているのか、薬剤による副作用がないかなどを確認する重要な役割を担っています。また検査技師は、病院の中で検出される細菌のすべてをいち早く把握し、大規模な院内感染を未然に防いでいます。詳しいことを秋田大学医学部附属病院感染制御部の感染制御認定薬剤師の加賀谷英彰さんと検査技師の小林則子さんにお話を伺いました。
 【11/14放送】病気をうつさない もらわない感染制御(1)
【11/14放送】病気をうつさない もらわない感染制御(1)秋田大学医学部附属病院 萱場広之さん・富田典子さん
今回から2回シリーズで院内感染を防ぐ取り組み「感染制御」についてをテーマにお送りします。医療施設には入院患者をはじめ、医療従事者、お見舞いに訪れる人など大勢の人が訪れます。感染症にかかりやすい抵抗力が落ちた人も少なくありません。感染制御というのは、こうした医療施設のなかで感染症をうつされたり、広げないようにしようという取り組みです。ことし、首都圏の病院で抗生物質がきかない多剤耐性菌による大規模な院内感染が明らかになりました。1回目の今回は、県内の医療施設でどのような管理が行われているのかなどについて秋田大学医学部附属病院感染制御部の萱場広之医師と富田典子感染管理認定看護師に伺いました。
 【11/7放送】あせらず確認!子どもの便秘
【11/7放送】あせらず確認!子どもの便秘秋田大学医学部附属病院 萱場広之さん
子どもにとって便秘は大変身近な症状です。便秘には、特に原因になる病気を伴わない慢性の便秘と、先天性の病気が原因のも便秘と大きく分けて2つのケースがあります。先天性の中には特殊な治療を必要とする疾患が含まれている場合もあります。また、特別な病気が原因ではない慢性の便秘の場合でも、対応を間違えるとお子さんや保護者が長い間つらい思いをすることがあり、正しい診断と対応が必要となります。症状や治療法などについて伺いました。
 【10/31放送】子どもの鼠径ヘルニア
【10/31放送】子どもの鼠径ヘルニアたむら船越クリニック 田村広美さん
鼠径(そけい)ヘルニアは、足の付け根の弱い部分から、腸などの内臓が脱出する病気です。特に子どもの場合は、30人に1人程度の割合で、生まれつき腹膜の一部が袋状に飛び出していることがあり、この袋の中に腸や卵巣などの内臓がはみ出すのが特徴です。早期に発見すれば安全に治療することができますが、放置するとはみ出した内臓が締め付けられ、壊死してしまうケースもあります。子供の鼠径ヘルニアを見つけるポイントと治療方法について伺いました。
 【10/24放送】これってでべそ?へそヘルニア
【10/24放送】これってでべそ?へそヘルニア秋田組合総合病院 畑澤千秋さん
へそヘルニアは、通常は命にかかわるものではなく、本来、1歳ごろまでには自然治癒する傾向が強い疾患です。しかし、あまりにも大きい場合やへその皮ふがたるんで、外見上、気になる場合には処置や手術が必要になることがあります。赤ちゃんの出べそには、へそヘルニアとへそ突出の2つのケースがあるといいます。なぜなってしまうのか、その成り立ちや治療法などについて伺いました。
 【10/17放送】くぼんだ胸を小さな傷で矯正
【10/17放送】くぼんだ胸を小さな傷で矯正秋田大学医学部附属病院 吉野裕顕さん
今週は、漏斗胸(ろうときょう)がテーマです。漏斗胸というのは、先天的に胸の中央部分がくぼんでいる病気です。子どもは大人にくらべて、ろっ骨が柔らかく骨の矯正がしやすいため、漏斗胸の手術は、小学生の頃に行うことが最も多くなっています。手術で最近、主流となっているのがNUSS(ナス)法と呼ばれる手術法です。この手術法は、胸腔鏡を使った手術方法で、小さな傷で手術することができ、傷あとも目立ちにくく、患者への負担も少ないというメリットがあります。漏斗胸というのは、どのような病気なのか、手術法などについてお話を伺いしました。
 【10/10放送】赤ちゃんのおう吐〜ミルクを吐いても大丈夫?〜
【10/10放送】赤ちゃんのおう吐〜ミルクを吐いても大丈夫?〜秋田大学医学部附属病院 森井真也子さん
今週は、吐乳がテーマです。赤ちゃんがミルクを吐くことは、決して珍しいことではありません。しかし、中には緊急で処置が必要な場合もあります。赤ちゃんは、どこが苦しいのか自分で症状を訴えることができないので、保護者が状態を見極めることが大切です。赤ちゃんがミルクを吐いたときに確認しなければならない注意点や、緊急で処置が必要な病気などについてお伺いしました。
 【10/3放送】健康管理に欠かせない〜高齢者の口腔ケア〜
【10/3放送】健康管理に欠かせない〜高齢者の口腔ケア〜秋田大学医学部附属病院 中田憲さん
今週は、お年寄りの口腔ケアがテーマです。食べ物を食べるのに大切な口。その口の手入れをすることは、お年寄りが健康を維持するための大切な要素です。お年寄りは抵抗力がないため、口の中の細菌から悪い病気に感染してしまう危険性があります。このため、口の中を手入れして清潔に保つことで、病気に強い健康な体を保つことができるといいます。口腔ケアを怠ると、どのようなことが起きるのか、またケアの仕方、注意点などをお伺いしました。
 【9/26放送】障がい者歯科〜全身麻酔での治療も〜
【9/26放送】障がい者歯科〜全身麻酔での治療も〜県医療療育センター 猪狩俊郎さん
今週は、知的障がいや発達障がいの患者さんを専門に治療する障がい者歯科がテーマです。障がいを抱えた人は歯科医院で治療を行うのが遅れてしまい、むし歯や歯肉炎が進んでしまっている場合があるといいます。また、痛みのために歯磨きをしないでいると、歯ぐきがはれて痛くなり、ますます歯磨きをしなくなるため、むし歯がさらに悪化してしまうという悪循環をたどってしまうこともあります。一般の治療より工夫を凝らして行われる治療方法やむし歯予防のための注意点を県立医療療育センター・歯科の猪狩俊郎さんにお伺いしました。
 【9/19放送】口が開かないと要注意! 顎(がく)関節症
【9/19放送】口が開かないと要注意! 顎(がく)関節症秋田大学医学部附属病院 高野裕史さん
今回は顎(がく)関節症をテーマにお送りします。顎(がく)関節症というのは、あごの関節やその周りにある筋肉に負担がかかり、発症する病気です。怖い病気ではありませんが、日常生活の悪い習慣が積み重なって発症している場合も多くあり、知らず知らずのうちに発症しているケースもあるといいます。特徴的な症状や治療方法などを紹介するほか、番組の中で一緒に自己チェックを行い、予防するための日常生活での注意点などについて伺いました。
 【9/12放送】インプラント(人工歯根)で快適!食生活
【9/12放送】インプラント(人工歯根)で快適!食生活秋田大学医学部附属病院 福田雅幸さん
今回は歯のインプラント(人工歯根)治療をテーマにお送りしました。インプラントはブリッジや入れ歯に替わる歯の治療法で、歯を失って悩んでいる方にインプラントと呼ばれる金属チタンで出来た人工歯根を埋め込み、かみ合わせを作る比較的新しい歯の治療法です。 一体どのような治療法なのか、また従来の治療法との違いや治療を受ける際の注意点などを伺いました。
 【9/5放送】知ろう!緩和ケア(2) ホスピスでの緩和ケア
【9/5放送】知ろう!緩和ケア(2) ホスピスでの緩和ケア外旭川病院 嘉藤茂さん
前回に引き続き、緩和ケアについてをテーマにお送りしました。ホスピスと聞いて、実際にどのようなことを行う病棟なのか、みなさん簡単にイメージがつくでしょうか。ホスピスというのは、患者が抱えるあらゆる痛みを和らげようという医療、緩和ケアを専門に提供する病棟のことです。終末が近い患者さんはもちろん、一般的に外来や在宅でつらさを和らげることが難しい患者さんが利用します。しかし、ただ死を待つだけの病棟など、残念な誤解をしている人も少なくありません。外旭川病院ホスピス長の嘉藤茂さんに、対象となる人やどのような病棟なのか、また入院するまでのプロセスなどを伺いました。
 【8/22放送】知ろう!緩和ケア(1) チームで取り組む緩和ケア
【8/22放送】知ろう!緩和ケア(1) チームで取り組む緩和ケア秋田大学医学部附属病院 片寄喜久さん
今回と次回は緩和ケアについて2回シリーズでお送りしました。緩和ケアという言葉は耳にしていても、実際にどのようなことをするのか、よくわからないという人も少なくありません。がん患者さんなどに対して行われる医療ですが、治療が出来なくなった方が行う、がんの終末期などと誤解している方もいます。緩和ケアは患者が抱えるあらゆる痛みを和らげようという医療で、終末期だけに行うものではなく、初期の段階から切れ目なく行われます。1回目の今回は、緩和ケアというのはどういう医療か、どこで受けられるのかなどについて秋田大学医学部附属病院緩和ケアセンター長の片寄善久さんに伺いました。
 【8/15放送】変わる抗がん剤治療(3) がん医療のコーディネーター
【8/15放送】変わる抗がん剤治療(3) がん医療のコーディネーター秋田赤十字病院内科 武藤理さん
「がん薬物療法専門医」は、抗がん剤治療の専門医です。がん治療に関わる様々な部門と連携して、患者に最適な治療計画をコーディネートするのが役割です。これまでは、手術を担当する外科医が、抗がん剤治療も行うのが一般的でしたが、抗がん剤治療の飛躍的な進歩に伴い、専門医の必要性が高まっているのです。番組では、がん医療のコーディネーターとして、患者のトータルケアを目指す「がん薬物療法専門医」の役割と、普及に向けた課題を伺いました。
 【8/8放送】変わる抗がん剤治療(2) 外来診療で快適に
【8/8放送】変わる抗がん剤治療(2) 外来診療で快適に秋田大学医学部附属病院腫瘍内科 大塚和令さん
抗がん剤治療は、副作用が伴うため入院して行うのが一般的です。しかし、副作用が少ない新しい抗がん剤の開発や、医療技術の進歩に伴い、外来で治療を行う例が増えています。日常生活を送りながら、安全に抗がん剤治療を行えるようになったことで、生活を犠牲にすることなく、がんと共存していくことができるようになってきています。番組では、増えつつある外来での抗がん剤治療の現状と課題について伺いました。
 【8/1放送】変わる抗がん剤治療(1) がん治療を変える分子標的薬
【8/1放送】変わる抗がん剤治療(1) がん治療を変える分子標的薬秋田大学医学部附属病院腫瘍内科 柴田浩行さん
抗がん剤は、手術が難しい「進行がん」に対し、がん細胞の増殖を抑える薬剤です。症状の緩和や延命などの効果が期待できる一方で、正常な細胞まで攻撃してしまうため、様々な副作用が伴います。しかし、10年ほど前から、副作用の少ない新しい抗がん剤「分子標的薬」が普及し、抗がん剤治療の可能性が大きく広がっています。番組では、新しい時代の抗がん剤「分子標的薬」の特徴と課題について伺いました。
 【7/25放送】超音波検査で早期発見〜すい臓がん〜
【7/25放送】超音波検査で早期発見〜すい臓がん〜本荘第一病院 柴田聡さん
今回はすい臓がんをテーマにお送りします。すい臓がんは、初期の場合、典型的な症状があまり見られません。このため発見が遅れてしまう場合があり、早期発見がなかなか難しいがんだといわれています。番組では、すい臓の働きや見逃せない症状のチェックポイント、定期的に超音波検査を続けることの重要性などについて伺いました。
 【7/18放送】お尻からの出血に注意!
【7/18放送】お尻からの出血に注意!小泉病院肛門外科 伊藤正直さん
重大な病気が原因の可能性もある「お尻からの出血」についてお伝えします。「お尻からの出血」の原因として最も多いのが「痔」で、日本人の3人に1人がかかるとも言われます。しかし痔と似た症状を伴う病気の中には、大腸がんなどの命に関わる重大な病気もあります。番組では「お尻からの出血」の多くを占める「痔」の症状や予防法を伝えるとともに、痔と間違えやすい、大腸がんなどの病気について伺いました。
 【7/11放送】高齢者で増加! 鼠径ヘルニア(脱腸)
【7/11放送】高齢者で増加! 鼠径ヘルニア(脱腸)市立秋田総合病院 伊藤誠司さん
今回は鼠径ヘルニア(脱腸)をテーマにお送りします。鼠径ヘルニアは、お腹の壁である腹壁の一部が弱くなり、太ももの付け根あたりに腸や脂肪などの内臓が飛び出してくる病気です。この病気は、高齢化にともなって中高年の男性や高齢者に増えているといいます。自然に治ることはなく、薬で治すこともできないため、手術をすることが治療の基本になっています。番組では、どうして起きるのか、その原因や最近主流となっている手術方法を伺いました。
 【7/4放送】食生活の変化で急増! 〜大腸がん〜
【7/4放送】食生活の変化で急増! 〜大腸がん〜秋田大学医学部附属病院消化器外科 宮澤秀彰さん
大腸がんは、食生活の欧米化に伴い患者が急増しています。特に女性では死亡する人が最も多いがんになっています。がんが進行し、しゅようが大きくなると、お腹の張りを感じるようになりますが、早期では症状が無いことがほとんどです。早期発見には検便などの検診を定期的に受けることが大切。番組では、患者が急増している大腸がんの治療法と予防のポイントを伺いました。
 【6/27放送】突然の胸の痛み…気胸
【6/27放送】突然の胸の痛み…気胸仙北組合総合病院 中川拓さん
今回のテーマは、気胸。酸素と二酸化炭素を交換する重要な臓器である肺。気胸は、何らかの原因でこの肺を包んでいる薄い膜である胸膜に穴があいて、空気が漏れ、肺が縮んでしまう病気です。主な症状として、突然起きる胸や背中、肩の痛みや息苦しさがあります。患者は背が高いやせ形の若い男性やタバコを吸う中高年が多く、一度かかってしまうと、何度も繰り返し再発も多いといいます。番組では、手術をはじめとする最新の治療法や症状などを詳しく紹介していきました。
 【6/20放送】吸わない人も油断大敵〜肺がん〜
【6/20放送】吸わない人も油断大敵〜肺がん〜秋田大学医学部附属病院呼吸器外科 南谷佳弘さん
肺がんは、たばこを吸う人に多い病気ですが、その半分は喫煙とは関係のないタイプのがんです。たばこを吸わなくても、肺がんにはかかる可能性はあるのです。早期に発見すれば手術で切除し、治すことができますが、自覚症状が少ないため、定期的に健診を受けることが大切です。番組では、がんの中で最も死亡数が多い「肺がん」の治療法と早期発見の大切さについて、伺いました。
 【6/13放送】自分でチェック!乳がん
【6/13放送】自分でチェック!乳がん秋田大学医学部附属病院・乳腺内分泌外科 伊藤亜樹さん
今回のテーマは、乳がん。乳がんは、日本人女性の約20人にひとりがかかるといわれている病気。患者は年々増加していて、がんの中でも患者の年齢層が比較的低いのが特徴です。しかし、早い時期に見つけると患者に優しい治療を選択することができ、約9割の人が治るといわれています。早い時期に見つけるために、お勧めのチェック方法は自己検診。自分でチェックする際の詳しいポイントをお伝えします。このほか、医療機関で行われる検査方法についても紹介していきました。
 【6/6放送】胃カメラで早期発見!〜食道がん〜
【6/6放送】胃カメラで早期発見!〜食道がん〜秋田大学医学部附属病院食道外科 本山悟さん
食道がんは、がんの中でも悪性度が高く、症状が出てからでは治療が難しい病気です。リンパ節に転移しやすく、心臓や肺、大動脈など重要な臓器に取り囲まれているため、手術も難しいものになります。しかし、早期の段階で発見できれば、内視鏡で切除するなどして高い確率で治すことが出来ます。番組では、秋田の県民病ともいえる「食道がん」の治療法と、早期発見の大切さになどについて伺いました。
 【5/30放送】慢性的な痛みを取り除く ペインクリニック
【5/30放送】慢性的な痛みを取り除く ペインクリニック平野いたみのクリニック 平野勝介さん
今回は、「慢性的な痛みを取り除く ペインクリニック」と題してお送りしました。全身のあらゆる痛みの診断と治療を目的とした診療科であるペインクリニック。長く続く痛みは、そのまま我慢して放置していると、痛みの悪循環が起こってしまい、病気やケガの治癒が遅れたり、さらには神経の損傷などから他の疾患を誘発してしまうケースがあるといいます。痛みの悪循環はなぜ起こってしまうのか、痛みが長く続いている場合はどのように対応すればよいのか、またペインクリニックの主な治療法などを紹介しました。
 【5/23放送】手術後の痛みを和らげるために
【5/23放送】手術後の痛みを和らげるために秋田大学医学部附属病院麻酔科 合谷木徹さん
手術後の痛みを和らげることで、体の回復を早めるポイントについてお伝えします。手術の後の痛みが長引くと体が疲れ、血流が悪くなり、傷の治りが遅くなることがあります。体の負担を減らし回復を早めるには、麻酔を使い痛みを適切に和らげ取り除くことが大切です。番組では、硬膜外カテーテルやブロック注射など、手術後の痛みを和らげる最新の治療法などについて伺いました。
 【5/16放送】PET検査が身近に
【5/16放送】PET検査が身近に秋田大学医学部附属病院放射線科 岡根久美子さん
保険の適用範囲が広がり身近になった「PET検査」についてお伝えします。PET検査は放射線を出す薬を注射し、体から出てくる放射線を撮影して診断する方法で、がんなどの検査に効果を発揮します。今年4月から、早期の胃がんを除く全てのしゅようについて保険が適用されるようになり、利用しやすくなりました。身近になった「PET検査」について伺いました。
 【5/9放送】がん治療最前線 高精度放射線治療
【5/9放送】がん治療最前線 高精度放射線治療秋田大学医学部附属病院放射線治療科 安倍明さん
今回は「高精度放射線治療」をテーマにお送りしました。
がんの患者さんにとって欠かせない放射線治療は、日々進歩しています。高精度放射線治療は、今年度中には秋田大学医学部附属病院で初めて導入される予定の最新の放射線治療法です。従来の放射線治療に比べて、がんの患部に適切に放射線をあてることができるため、これまでに比べて副作用が少ないといわれています。いったいどのような治療法なのか。また、従来の治療法とはどのように違うのか、治療を受ける際の注意点などもお伝えしました。
 【5/2放送】目の充血が治らない・・・脳の血管は大丈夫?
【5/2放送】目の充血が治らない・・・脳の血管は大丈夫?秋田大学医学部附属病院放射線科 高橋聡さん
脳こうそくや脳出血につながる「硬膜動静脈ろう」について伝えます。脳にある動脈から静脈へ血液が流れ込み、目の充血や腫れを引き起こします「硬膜動静脈ろう」は、診断が難しいため、結膜炎と間違われやすい。病気を見つけるポイントと、マイクロコイルを使った最新の治療法について伺いました。
 【4/25放送】検尿と腎臓病
【4/25放送】検尿と腎臓病秋田大学医学部附属病院小児科 土田聡子さん
小中学校で行われる「検尿」の大切さを伝えました。慢性腎臓病は自覚症状がほとんどないのが特徴。子供の時に発症し、そのまま大人になって悪化してから気づくケースが多い。学校の検尿は、腎臓病を子供のうちに発見するために行われています。症状がないうちに発見し適切に管理すれば、悪化を防ぎ良い状態を保ことができます。学校検尿と子供の腎臓病について伺いました。
 【4/18放送】子どもの健康(3)「けいれんにはあわてず対応」
【4/18放送】子どもの健康(3)「けいれんにはあわてず対応」秋田大学附属病院小児科 矢野珠巨さん
「子どもの健康」シリーズ、3回目のテーマは「けいれん」。子供は脳の発達が未熟なため、大人に比べてけいれんを起こしやすいと言われます。子供のいれんには主に熱性のけいれんと、熱がなくても起きる、てんかんなどがあります。突然。子どもにけいれんが起きると、つい慌ててしまいがちですが、数分で治まるものがほとんどなので、落ち着いて対応することが大切です。おう吐による窒息を防ぐために顔を横にするなど、子供のけいれんへの対応のポイントを伺いました。
 【4/11放送】子どもの健康(2)「正しく理解しよう!食物アレルギー」
【4/11放送】子どもの健康(2)「正しく理解しよう!食物アレルギー」秋田組合総合病院小児科 小松真紀さん
「子どもの健康」シリーズ、2回目のテーマは「食物アレルギー」。食べ物を食べた後で、肌が赤くなったり、呼吸が苦しくなったりと、体に異常な反応が出る食物アレルギー。小さい子どもに多くみられますが、子どもはなかなか症状を訴えることができないため、周囲の人達が症状を正しく理解することが重要です。子どもが食物アレルギーを引き起こす原因や診断方法、治療方法などのポイントを伺いました。
 【4/4放送】子どもの健康(1)「春がチャンス!肥満をチェック」
【4/4放送】子どもの健康(1)「春がチャンス!肥満をチェック」秋田大学附属病院小児科 高橋郁子さん
「子どもの健康」シリーズ、1回目のテーマは「肥満」。秋田県は子供の肥満が多いと言われています。子供の肥満で問題なのは、内臓に障害が発生しても、症状の無いまま進行するため、気がつかないうちに健康を害していることが多いことです。脂肪肝による肝機能障害や動脈硬化は子供のうちから徐々に進行することが分かっています。春は学校で健康診断が行われるため、子供の肥満を発見するチャンス。肥満による健康上の問題から子供を守るためのポイントを伺いました。
 【3/28放送】上手にのりこえよう 更年期障がい
【3/28放送】上手にのりこえよう 更年期障がい山本組合総合病院 松井俊彦さん
更年期とは、「性成熟期から老年期への移行期で、50才前後にくる閉経周辺の時期」のことです。この時期には卵巣から分泌される女性ホルモンの低下によって“更年期障がい”と呼ばれるさまざまな症状が起こります。だれもが迎える心と身体の転換期。その上手な過ごし方を伺いました。
 【3/21放送】中年女性は要注意!子宮体がん
【3/21放送】中年女性は要注意!子宮体がん秋田赤十字病院産婦人科 佐藤宏和さん
子宮体がんは、胎児を育てる子宮本体の内部にできるがんで、40歳代後半から50歳代の「更年期」前後から患者数が増加するのが特徴。食生活など生活スタイルの欧米化に伴い、患者数は全ての年代で増加傾向にあります。早期に発見し治療することが大切ですが、注意しなければけないのが「子宮がん検診」。検診や人間ドックで単に「子宮がん検診」という場合「子宮頸がん」のみの検査を指すことが多いため。心身共に不安定な更年期前後から増加する「子宮体がん」について伺いました。
 【3/14放送】子宮頸がんは予防できる
【3/14放送】子宮頸がんは予防できる中通総合病院産婦人科 利部徳子さん
子宮頚がんは、子宮の入り口周辺にできるがんで、20歳代から30歳代の妊娠・出産年代での発症率が高いのが特徴。初期はほとんど自覚症状がないが、進行すると出血やおりものなどの症状が現れ、子宮を摘出せざるを得ないケースもある。子宮頸がんは、検診によってがんになる前に発見することができ、子宮を温存して治療することができる。しかし日本では受診率が約20パーセントと低く、特に若い女性の受診率が低くなっている。若い女性の間で急増している、子宮頸がんを予防する方法などを伺いました。
 【3/7放送】激しい月経痛をきたす子宮内膜症
【3/7放送】激しい月経痛をきたす子宮内膜症市立秋田総合病院産婦人科 福田淳さん
子宮内膜症とは、子宮内膜が卵巣やお腹の中など他の場所に存在する病気で、強い月経痛が特徴。女性の生活の質を著しく損なう病気で、近年増加傾向にあります。子宮内膜症が進行してくると、卵巣内に古い血液がたまり、チョコレートのような色の内容物を含むふくろを作ります。これをチョコレートのう胞と言い、感染したり、破裂したりすると激しい腹痛を起こすこともあります。不妊症の大きな原因でもある子宮内膜症の治療方法などについて伺いました。
 【2/28放送】胃がんは早期発見が最も大切
【2/28放送】胃がんは早期発見が最も大切秋田組合総合病院 渡部博之さん
平成20年に胃がんで亡くなった秋田県の方は、746人。秋田県の胃がんの死亡率は、全国ワースト1です。胃がんは早期の段階では自覚症状がないのが特徴です。転移のない早期の状態で発見された胃癌の場合、切除手術により9割以上の方が治ることがわかっています。このため、定期的な検診が重要で初期の段階で見つけることが大切です。胃がんの症状と治療方法について伺いました。
 【2/21放送】C型肝炎
【2/21放送】C型肝炎市立秋田総合病院 小松眞史さん
日本では、年間3万4千人が肝臓がんで亡くなっています。このうち7割の方は、C型肝炎が原因とされています。C型肝炎のウイルスに感染しているかどうかは採血検査で診断でき、県内の保健所では無料で行っています。治療は、体からC型肝炎ウイルスを排除する根治的治療と、肝臓の炎症を抑え、肝臓がんへの移行を遅くする対症療法があります。自覚症状に乏しいC型肝炎について伺いました。
 【2/14放送】ズキンズキンと脈打つ痛み 片頭痛
【2/14放送】ズキンズキンと脈打つ痛み 片頭痛市立横手病院 塩屋斉さん
片頭痛は、こめかみから目のあたりがズキンズキンと脈打つように傷む頭痛のことで、脳にある血管を取り囲む三叉神経の炎症が原因と考えられています。日本ではおよそ840万人もの人がこの片頭痛で悩んでいて、特に20歳代から40歳代の女性に多い。頭痛の際は、動いたり歩いたりしただけで痛みが強くなるほか、吐き気を伴ったり、普段は気にならない程度の音・光・臭いが煩わしくなり、仕事・家事・学業など日常生活に支障を来たしてしまいます。片頭痛がおきたときの対処方法と、治療方法などについて伺いました。
 【2/7放送】手足がふるえる パーキンソン病
【2/7放送】手足がふるえる パーキンソン病秋田大学医学部附属病院神経内科 菅原正伯さん
パーキンソン病になると、手足がふるえ、動作がにぶくなる。足の運びが小さくなるなどの症状があらわれます。中高年に多い病気です。ドパミンの減少が原因とされています。治療には、少なくなっているドパミンを飲み薬で補う方法があります。多くのパーキンソン病患者さんに対してお薬は有効とされています。手足がふるえるパーキンソン病の詳しい症状と治療方法などについて伺いました。
 【1/31放送】骨が折れていないのに 肩の痛みが続くのは
【1/31放送】骨が折れていないのに 肩の痛みが続くのは中通総合病院整形外科 畠山雄二さん
骨が折れていないのに肩の痛みが続く「腱板断裂」を取り上げます。腱板は、肩を動かす筋肉で、痛めてしまう原因の多くは、年齢を重ねることで、腱がすり減って弱くなってしまうため。また、肩や腕を強くぶつけたり、ひねったりすることも大きな原因とされています。患者は、特に60歳以上の人に多いです。肩の痛みが続く腱板断裂の症状と治療方法などについて伺いました。
 【1/24放送】じっとしていても治らない ひざの痛み
【1/24放送】じっとしていても治らない ひざの痛み市立秋田総合病院整形外科 木村善明さん
年齢とともにひざの関節がすり減り変形する「変形性ひざ関節症」を取り上げます。この病気は中高年に多く、動きはじめるときにひざが痛みます。軽度から中度の変形性ひざ関節症には、イスに座って足を伸ばす運動療法が効果的で、症状が進んだ状態の場合は、ひざの骨を削ったり、関節を人工関節に置き換える手術が行われます。変形性ひざ関節症の症状と治療方法などについて伺いました。
 【1/17放送】足のしびれは腰が原因だった!?
【1/17放送】足のしびれは腰が原因だった!?秋田組合総合病院 小林孝さん
歩いていると足がしびれてくるという症状について取り上げます。これは、体の中心にある脊柱管が狭くなることが原因のひとつ。しびれは、おしりから太ももの裏側、そしてふくらはぎ、足の裏と広がっていきます。ひどい場合には歩くことができなくなることもあります。症状が軽い場合は、薬で治療する方法があります。また、手術での治療は、骨を削る方法と、金属で骨を固定する方法があります。腰部脊柱管狭窄症の治療方法などについて伺いました。
 【1/10放送】骨が原因で寝たきりにならないために
【1/10放送】骨が原因で寝たきりにならないために秋田大学医学部附属病院 粕川雄司さん
圧倒的に女性に多い病気、「骨粗しょう症」について取り上げます。骨粗しょう症は、骨がもろくなる病気で、それ自体は特に症状はありません。しかし、骨がもろくなるために骨折しやすくなり、太ももの付け根の部分が骨折すると、寝たきりになる可能性が高まるといいます。骨の量は、40歳くらいまでは一定とされますが、その後は次第に減少していきます。また、加齢に伴う骨の量の減少は、閉経後の数年が最も大きくなるといいます。予防と治療方法などについて伺いました。
); ?>)
); ?>)