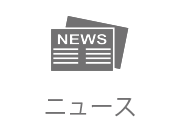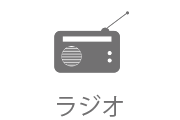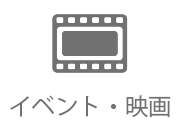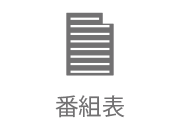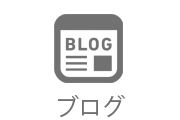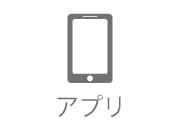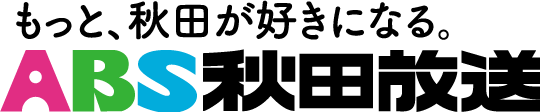番組審議会リポート|
PROGRAM COUNCIL REPORT
第665回番組審議会が昨年の12月26日に開かれました。議題は「2025年を振り返って」でした。
審議委員からは
今年1年の番組を振り返ってみると、テレビ・ラジオともに、硬派で取材力の高さを感じる内容が多かった。特に今年は戦後80年ということで、8月の「平和へのミッション」では、取材の過程で新しく分かった事実があったり、これまで知られていなかったことに光を当てるなど、時間の経過とともに取材が難しくなっていく戦争について、幅広い世代に考えてもらう機会を与える番組だった。
秋田について、知らなかったことを教えてもらえる番組が多かった。クマであったり、ハタハタであったり、その後どうなったのかを知りたくなる内容だった。インターネットの映像配信サイトなどでは、制作者が自分の好きな情報だけを発信しているように感じるが、合評対象となった番組は、いずれも色々と考えられて作られた番組が多く、若い人たちにも見てもらいたいと思った。
1年を通じて、人物にスポットを当てた番組が印象に残った。高次脳機能障害を持った女性、いぶりガッコづくりに取り組む人、新知事、そして墜落したB29を追い続ける探検家、と、秋田にはこんなにも多くのたくましい人たちが生きているのだ、ということを実感した。秋田の魅力をアピールするとき、財力やブランド力などではほかの地域に比べて劣るかもしれないが、こういう素敵な人物がたくさんいる、ということを訴えるという方法もあるのではないか、と思った。
今年の番組の中で印象に強く残っているのは、高校のラグビー部を取り上げた番組といぶりガッコづくりに取り組む女性を取り上げた番組だった。どちらも若い人が主人公で、見ていて明るい気持ちになれた。
番組審議会での制作者からの説明を聞いていて感じることだが、番組を制作する記者やディレクターに、しっかりした人物がそろっているように思う。社員の間で受け継がれてきたものと思うが、こうした伝統は受け継いでいって欲しい。
B29の墜落と生存兵を追った番組は、新聞やほかの放送局を動かし、さらにはアメリカ大使館も反応を示すなど、ムーブメントとも言うべき反響を呼んだ。このきっかけが秋田放送の報道で、しかもこれが終わりではなく新たな動きの端緒ともなっていることは高く評価したい。
といった意見が上がりました。
第664回番組審議会が11月12日に開かれました。合評番組は「たどるB29墜落 ~秋田の痕跡 生存兵の足跡~」でした。
審議委員からは
終戦直後に男鹿半島で墜落したB29について、生存兵による事故現場訪問の映像を手掛かりに様々な取材の蓄積が紐づいて、深い内容の番組になっていた。35年前の訪問の様子が動画で残っているというのはインパクトが強いものだと感じた。また、深い山の中にあったB29の残骸を探す際には、ドローンを使って上空から撮影したり、逆に地上で深い藪をかき分け、急な斜面でカメラマンが滑り落ちてしまう映像をそのまま使うことで、探索の大変さが伝わってきた。見ごたえのある番組だった。
アメリカの博物館で撮影したB29の機内の映像は非常に貴重なものだと感じた。特に、生き残った兵士が乗っていた、尾翼近くの席の狭さを見ると、墜落した時にはどれほど怖かっただろうか、その小さな席にたった一人で座り、乗組員の中でただ一人生き残ったことによる心の傷はいかに深いものだったろうか、ということが映像から偲ばれた。
生存兵の家族をアメリカに訪ねた時の映像は、感慨深いものがあった。子、孫、ひ孫、玄孫、皆さんがそろっている映像。男鹿の人たちが生存兵を助けなければ、この家族は誰もいなかったのだ。当時のことを知っている人が元気なうちに、このご家族に男鹿に来てもらい、亡くなった兵士の慰霊碑を見てもらいたいと思った。この番組を通じて昔のことを知ることができたと同時に、男鹿の人たちのやさしさを知ることもできた。
生存兵は事故のことについて多くを語らなかったと家族は言っていた。それは戦争による心の傷が原因だろうということだった。しかし、45年後に男鹿を訪ねて自分を助けてくれた人たちに出会い、亡くなった仲間たちの慰霊碑があったことを知り、そのことを遺族たちに連絡していたという。彼はそのことで救われたのではないか。番組の進行とともに謎が紐解かれていくようで、まるで物語を見ているように感じた。
この番組は、何らかの高い評価を受けていいものだと思う。秋田という、戦争とは直結しないような地域にこういう傷跡が残っていたことを掘り起こし、そこでかつての敵国の兵士が地元の人々の手によって救助されていた、彼が生き残ったことで生れた家族たちにも取材に行き、現場で見つかった残骸をアメリカにある実物と突き合せた、など、今までになかったような情報が満載されている。そしてそれらが、戦争というものはあってはならないのだ、という主張にしっかりと結びついている。こうした様々な点が評価されてほしい、と感じている。
といった意見が上がりました。
第663回番組審議会が10月28日に開かれました。合評番組は「ぶらり途中下車の旅 秋田編」でした。
審議委員からは
秋田県内を列車に乗って途中下車しながら旅するというこの番組、旅人に選ばれた落語家の林家たい平さんと地域の人たちとのやりとりが全体を通して温かみがあったな、というのが印象に残っている。
訪れた場所が、田沢湖高原、角館、大曲と、メジャーな観光地だったが、登場する店やクローズアップする見どころや商品が、珍しいものや目新しいものが多かった。こうした全国区のタレントが登場する番組ではおなじみのものが取り上げられることが多いのだが、この番組では秋田の地元に住んでいる人も楽しめる内容となっていた。
旅人のたい平さんは、落語家さんらしくお話にしゃれを交えていたり、言い回しも機転が利いていてすてきだな、と思うところがたくさんあった。角館の駅に降り立ったたい平さんが、「長屋門みたいに風情のある建物がある」とか、タクシー乗り場や交番まで風情がある、など街並みを見て色々な発見をしていた。県外からの観光客はこうした目線で見ているんだな、ということが分かって、秋田の魅力をアピールする上でも参考になった。
全体に温かい雰囲気の番組だと感じた。たい平さんが色々なものを食べるときとてもおいしそうに食べている、感動を伝えるときも心から伝わってくるような感じがして好感が持てた。
自分の地元の場所を多く回ってくれたので、とても楽しく見ることができた。番組の最後に黄色く染まった田んぼの中を1両の列車が走っていく姿が印象的だった。たい平さんという人選もとてもよかったと思う。
この番組は関東方面で放送しているのを何度か見たことがあるが、地元の人も存在は知っていたが入ったことはない、というような店や場所を取り上げていた。今回の番組もそうだが、リサーチはかなり幅広くやったのではないか。視聴者の興味をうまく引っ張り込む、巧みなスポットの選択だった。
秋田のことは知っているつもりになっていたが、地元が持っている魅力は常に更新されている、と感じた。家業を継いだり事業を継承したりして、新しい履物、新しいお菓子、奇抜なお弁当などが生まれている。しかもそれを担っている人たちが、遊び心があって明るく楽しそうなのが印象に残った。そこに、我々の生活を豊かにしたり、奥行きをもたらしたりしてくれる手がかりが感じられる番組だった。
といった意見が上がりました。
); ?>)
); ?>)